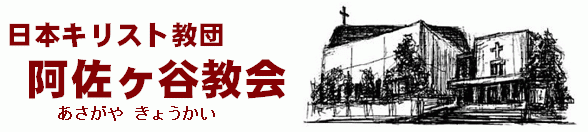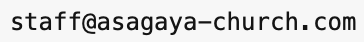◇有名な、放蕩息子の譬えである。弟息子は、父親の財産の生前分与を要求する。彼にとって父親はカネでしかない。彼が遠い国へと出かけるのは、今の自分は、自分ではないという意識の反映である。彼はそこで、酒、物、セックスを自由に謳歌し、自分の人生を得たと考える。しかし彼には虚しさが残る。その虚しさを消そうとしてまた無計画にカネを使う。こうして彼はすべてを使い果たしてしまう。虚しさは絶望であり、放置すれば、人は既に死んでいるに等しい。しかし生物的には生きざるを得ないから、虚しい生活を続ける。この弟息子は、そうした人間の典型である。
◇しかし彼は我に返る。意識の中で消したはずの父親を思い出す。言い換えれば、神に創造され、愛されている存在であることを思い起こすのである。父親は強権的ではなく寛大である。この息子に「雇人の一人に」という告白が生じる。罪の悔い改めである。父の元に帰るならばどんな形にしろ生きながらえさせてくれる。父親は、この息子を勘当する気などない。弟息子の帰りを待ちわびていたのである。そしてこの息子を遠くに見つけた時、父親は走り出す。神の愛が走ってくるのである。父親がこの息子をひしと抱いたとき、弟息子は罪の告白をする。しかし父親はその言葉を途中で遮る。父と同等の衣を着せ、同等の権威の象徴である指輪をはめてやり、関係を回復する。そして弟息子は生き直すことができるのである。
◇虚しさとは、有限なものを無限と錯覚し、永遠でないものを永遠と思い込み、そこに真実の愛があると錯覚することに対する神様からの警報装置である。この弟息子にただ一つの功績がある。「思い起こした、我に返った」ことである。父親の大きな愛に帰ることができる。そこで生きることができることを思い出したのである。
◇たとえ世の生活で傷つき、ボロボロになっても、この礼拝に戻って生き直すことができる。そのことは、ここで礼拝している人々が証ししている。
(要約:太田好則)